甲大神社 ― 2020年05月06日 13時52分24秒
天慶3年 西暦940年 2月14日
平将門は藤原秀郷の放った矢で
顳顬を射抜かれ絶命した
吾こそは新皇であると
この関東の地で独立国家を築くことを宣言し
日本中を震撼させた男だ
それ以後1000年を超え
今日に至るまで
この国にそんな豪快な男は
一度も登場していない
リーダーを失い
残された一族郎党は
住み慣れた土地を捨て四散する
残党狩りは峻烈を極め
国を挙げての大捜索が行われた
遠くへ遠くへ遠くへ
関東には広く
落人の伝説が無数に残る
千葉県市川市にある甲大神社には
将門の兜を祀っているという伝承がある
そして武士がこの社の前を通ると
必ず落馬するのだという
一見意味不明な話が添えられているが
まるで将門が
残党狩りの追手から
守ってくれてることを伝えているように
私には思える
江戸川に沿ってこの辺りは
中世から製塩業が盛んであったらしい
大和田という地名が残っているが
中世のある時代に大和田村は
稲荷木村と河原村の間の地に
塩焼稼業の為
全村集団移転した
という記録がある
将門の乱から僅か50年程
この大和田村に兜宮
現在の甲大神社が勧請されている
この2つの事柄は
決して無関係ではないだろう
恐らくは落人あるいは
将門に何らかの所縁のある集団が
職業を得て定住を図った
と考えていいのではないだろうか
将門に関連する寺社や史跡は
日本中に無数に存在する
もちろん調伏派のものも多数あるが
シンパもやたら多くある
この甲大神社もその一つであろう
将門という男は
それほど信頼と敬意を抱かせ
人々を惹きつけてやまない
リーダーであったということだ
危機的状況の中で
私達の行く道を
明確に自分の言葉で語ってくれる
そんなリーダーを求めることは
果たして大それた願いなのかしら
人の悲しみのわからないぼんぼんでは
そりゃあ無理だぜ


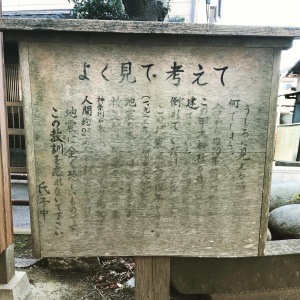
甲大神社
千葉県市川市大和田2-5-4
鳥見神社 ― 2019年04月21日 17時13分23秒
激しい戦の末
饒速日ニギハヤヒの王朝は敗北した
ニギハヤヒの娘である御歳ミトシが
磐余彦つまり神武天皇の妃となることで
政治的決着を図ったのだろう
以後大和朝廷の支配が始まり
それは新しい令和の世にまでも繋がっている
一方で主人を失った人達はどうなっただろう
他所から来やがってと腹の中では思いながらも
上手いこと折り合いをつけて
その実権を掌握し続けたのが
物部氏ではなかったか
拠点に留まり続け
ある時期まで実質の政権を揮っていたのは
歴史が示す通りである
また一方で
こんな所に居られるかと
東へと移動する物部ほかニギハヤヒ一派もいた
神武軍と激しくぶつかり合った
長髄彦もまたその一派
彼らがその後
蝦夷と呼ばれるようになったという説もある
そんな一派が恐らく
たどり着いて暮らしを始めた場所の一つが
千葉の利根川と印旛沼に囲まれた辺り
鳥見神社という神社が
この周辺だけに20社以上確認できる
祭神は言うまでもなく
饒速日命
彼等は再起を決して祖神を祀り
その日を延々と待ち続けていた
のかもしれない
白井市富塚にある鳥見神社は
富士講の石塔や無数の庚申塔がズラリと並び
まさに民間信仰のオンパレードといった境内で
周りは今や新築の家が立ち並ぶニュータウン然とした
何ら面白味もない風景の中にあって
古代からずっと繋がる歴史が
ここにはあるのだよと言われてる気がするそんな
素敵な神社だ
そして極め付けは
なかなかに珍しい歓喜天の石塔が
残されていることだ
筑波山に嬥歌カガイという伝統が嘗てあった
カガイの夜は年齢・未婚既婚を問わず
誰もが自由に一夜の性の楽しみを
享楽することが許されていたそうだ
こぞって人々は山に登り
女房は亭主を
亭主は女房をおいて良い相手を物色し
酒を飲み乱痴気騒ぎの狂乱の中
あちこちで
老人が年端もいかぬ娘を抱いたり
艶かしさの残る老婆が青年と
卑猥な遊びに夢中になるという有様
カガイはそれこそ古代からあったようだが
そこに後から入ってきた密教が結びつき
信仰形態として確立していったらしい
歓喜天というヒンドゥー教の神が
仏像として信仰の象徴となり
聖天信仰といって全国に拡がっている
歓喜天は像の頭を持つ神が
抱擁し交合した姿で描かれる
あの悟りすました仏像達とはえらい違いなのだ
あまりにエロいので各寺では秘仏にして
見せないようにしているらしい
ここ鳥見神社にある石塔は
何気なく参道脇に置かれていて
写真撮影もオッケー
絡めあう腕と鼻
恍惚の表情が何ともいい感じ
カガイ的な風習が此処らにもにあったのかは
もう解りはしないが
江戸時代のものらしい神社建築にも
エロスな仕掛けが施されている
拝殿の裏面の彫刻だ
二十四孝という中国の書物があって
孝行が特に優れた人24人の
エピソードを綴るつまらない書だが
その中の唐夫人という女性の話
唐夫人の姑は年老いて歯が無くなって
物が食べれなくなって
どんどん衰弱していく
唐夫人は自分の乳を飲ませ
姑を救った
というなんだかよくわからない話
これが壁面に彫られているのだが
どう見ても乳を吸っているのは
衰弱した老婆ではなくギラギラした男の姿で
乳房を露わに乳首を吸われている唐夫人も
なんだか恍惚の表情をしているように見える
一見儒教的な厳正さを示す素振りで
実はエロスを喚起するという仕掛け
歓喜天とこのような壁の彫刻が
セットになっているところが多いらしい
悪神ビヤナカは世界に疫病をもたらし
人々は苦しみ次々と死んでゆく
人々の祈りに観音様が応える
観音様は美しい女性の姿となって
ビヤナカの前に現れる
ビヤナカの淫心は燃えさかり
彼女に迫った
彼女は言う
私の体が欲しいなら
仏法を守り人々を苦しめないと約束しなさい
ビヤナカは了解し
至上の恍惚状態を得続けている
観音様はそれを受け止め続けている
それが歓喜天
中身は兎も角
歓喜天にしても庚申講にしても
神社のお祭りもそうだな
人を結びつけ集わせる仕組みであったのだろう
このニュータウンに引っ越してきたたくさんの人を
結びつける仕組みは今あるだろうか



鳥見神社
千葉県白井市富塚694
海神稲荷神社 ― 2018年10月14日 17時51分31秒
街は賑わった
ネオンは永遠に消えることがなく
酩酊と興奮に塗れた男共が
鼠の様に街路に溢れる
街灯の柱に凭れる男
燐寸の匂いにふと我に帰る
見上げると巨大な楼閣
まだ新しい木造の格子に
女の白い顔を見た
昭和3年
街道沿いに点在していた遊女屋を集約して
船橋の海神新地はオープンした
東京から遠征してくるほどの賑わいだったらしい
娼妓は何故か
山形県出身者が多かったという
空襲で焼けることもなく
近年まで妓楼の建物が残っていたらしいが
訪れたその地には
真新しいマンションが並んでいるだけだった
戦後
遊廓は赤線へと移行したが
それも束の間
今ではストリップ劇場も撤去され
ただの住宅街へと街は変貌していく
ひび割れたアスファルトの先に
子供用の自転車が停まる家々の中に
外壁を緑色に塗ったソープランドが現れる
たった1軒だけが取り残された姿は
異様で悲しい
意図されたものなのだろうか
妓楼の撤去された跡に
一本だけ当時の街灯と思われる柱が残っている
粗骨材を露出する風化したその柱は
それでもいつでも証言台に立ってやるさと
堂々とした風采で屹立している
赤黒く錆びて盛り上がった金属の枠材は
まるで老婆の女陰の様に
ぱっくりと口を開けて誰かを待っている
コンクリートやアスファルトでは
きっと此奴らを埋めきれない
土地が記憶している
男の孤独も
女の悲しみも
情念も怨恨も狡猾も狂気も
流した汗も涙も体液も
全部
染み込んで拭えやしない
恐らくは
遊廓の末端あるいは外側であった場所に
海神稲荷神社がある
境内で若いお母さんが小さな女の子を遊ばせている
遊女が娼妓がここをお参りしたかなんて
もう誰にもわかりゃしない




海神稲荷神社
千葉県船橋市海神1-22
葛飾八幡宮 ― 2018年09月30日 11時12分51秒
日本全国の神社の内
八幡神社が最も
その鎮座数が多いと言われている
神の託宣による政治システム
広範に人々を統治するのに
都合の良かった一時代があった
ということなのだろう
JR東日本の総武線の本八幡駅は
昭和10年の開業
駅周辺の町名である八幡が駅名の由来だが
鹿児島本線の八幡駅と混同を避ける為
本八幡としたとのこと
本八幡という地名は無いのに何故そうしたかは
真相不明だという
町名の由来は勿論
此処に葛飾八幡宮が鎮座しているからだ
今から1100年も前
宇多天皇の治世に
この関東の地にも
充分に統治システムが届いていたという訳だ
それにしても
本家は九州の宇佐八幡なのだが
駅名くらいは俺達が本家本元にしちまおうぜという
昭和初期の諸先達の気概と勢いが感じられて
大いに喝采を送らせていただきたい
と思う
それで思い出すのは昨今の
地名の命名のセンスの無さだ
さいたま市 ひたちなか市 かほく市
平仮名かよ
馬鹿にしてるのか
南アルプス市
決して故郷を思わざる
住所ではないが極め付けは
兵庫県三田市の
ウッディタウン
泣けてくるね
ローマ字打ちでなかなか打てないし
「地名の改竄は歴史の改竄につながる
それは地名を通じて長年培われた
日本人の共同感情の抹殺であり
日本の伝統に対する挑戦である」
(谷川健一「日本の地名」)
地名改竄に加担した行政や
有識者と言われる人たちは
どう落し前をつけてくれるのだろう
死ぬまで無責任に知ったことじゃないと
平気で生きていくのか
そんなことさえ感じられない鈍感さなのか
何年か前にあった
泉佐野市のネーミングライツは
ほとんど狂気の沙汰だ
ポシャって当たり前だな
だけど今回の
ふるさと納税は泉佐野市を応援したい
地方には必ず地域産品があるでしょと宣う大臣は
地域産品のない地方は
もはや地方でもないとでも言うのだろうか
皆んな知恵を絞って一所懸命やってるのに
全く腹の立つ話だ
泉佐野市は松坂市と同一の地層でつながっているとか
なんとか屁理屈とこじつけで
乗り切っていただきたいなあ
歴史を改竄しても平気でいられる頭では
機能不全の統治システムしか思いつかないのだろう
1100年前の人々に
昭和初期の先達に
真剣に学ぶべきだ


葛飾八幡宮
千葉県市川市八幡4-2-1
不知森神社 ― 2018年05月27日 18時24分08秒
もうどのくらい
此処にいるのか
何時から
此処にいるのか
俺はもう
こんな所にはいたくない
どうして
どうすれば
此処を出られるのか
呪いにでも掛かっているのか
知らぬ間に犯した罪の罰なのか
それとも
俺の頭が
どうかしてしまったのか
八幡の薮知らずと呼ばれる此の地は
往時から入ってはいけない禁足地として
全国に知れ渡っていた場所だそうだ
一度入ったら出られない
入れば必ず祟りがあると
駅から僅かに5分も歩くと
突如現れる鬱蒼とした竹藪
入ってはいけないという
タブーを
誰もが今でも守っている
知ってか知らずか
ペットボトルが中に捨てられていたりするが
捨てた人間はきっと
家に帰ってから熱を出したり
自転車がパンクしたりしたに違いない
市川市教育委員会が立てた説明板には
入ってはいけない理由が諸説あると書いてある
近くの八幡宮の行事の
魚を放す池の跡で
行事が途絶えた後も
入ってはならぬことだけが伝えられたと
訳のわからない結論付けをしている
諸説のもう一つに
将門の伝説がある
平将門平定のおり
平貞盛が八門遁甲の陣を敷き
死門の一角を残したので
此の地に入ると必ず祟りがある
というものだ
これもよくわからないのだが
将門打倒のため
此処に仕掛けを施したってことか
都合よく将門が此処に来ないことには
有効じゃないような気がするが
しかも将門が討たれた後も
仕掛けを解くのを忘れちゃって
今に至るということだろうか
貞盛しか解き方を知らねえんだよ
などと皆で溜息をついたのだろうか
これに関しては
平将門魔方陣という本で加門七海さんが
さらりと謎を解いている
薮知らずから東北
つまり鬼門の方角へ
辿っていくと
茨城県稲敷郡美浦村の辺りに
ぶつかるのだそうだ
そこは将門が守護神とした神仏を
将門自ら祀った場所で
つまりこの薮知らずは
将門の守護神を
今でも死門で封じ込め
将門の復活を或いは祟るのを
防御する
謂わばインフラシステムであったのだ
そりゃ疎かに破壊したり
好立地マンション建てたりは出来ないよね
行政サイド或いは国か?もきっと
秘密裏にこの事が
延々と受け継がれているに違いない
放射性廃棄物を10万年間埋めておく時も
この禁足地のシステムを使うと良い
その意味が忘却されてから後も
人々はきっと
そこには近づかないように
するだろうから



不知森神社
千葉県市川市八幡2-8
最近のコメント